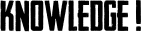第54回はモータージャーナリストの「九島辰也」さんにご登場頂きました。
BUBUがお届けする連載企画”ナレッジ” | Showcase.54「ダッジ・チャレンジャー×九島辰也」
文/プロスタッフ写真/内藤 敬仁
チャレンジャーのデザインは現代車両とは別物
アメリカ車の肩を持つわけではないが、ダッジ・チャレンジャーは素直にかっこいいクルマだと思う。長いボンネット、ワイドなボディ、リアピラーの角度と太さなんかがいい感じだ。それにサイドから見た時のドアガラスの小ささもいい。
では、なぜそんなカタチをしているか。それはご存知のように1970年デビューの初代をオマージュしているからだ。よって、現代のクルマのパッケージングからかけ離れたところにある。巨大な2ドアクーペはあくまでも当時のアメリカにおけるトレンドであり、時代と共に風化されてしまったシロモノだ。
 1970年登場の初代モデルをオマージュしたエクステリア
1970年登場の初代モデルをオマージュしたエクステリアそれが意味するのは、他の現代車両とは別物ということ。近年のトレンドはSUVであり、背が低いのはセダンと一部のスポーツカーくらい。2ドアクーペもないことはないが、5メートルを超えるシロモノはほぼ皆無だ。これと同じことはステーションワゴンにもいえる。今のところ昔のモデルをオマージュしたステーションワゴンは存在しないが、たとえば60年代のそれをどこかのメーカーが復刻させたなら、同じような現象が起きるであろう。トレンドとは別のところにあるそれは、きっとかっこよく見えるはずだ。
チャレンジャーを目の当たりにするとそんなことを感じる。“レトロモダン”とはよく言ったもので、いい塩梅に当時のシルエットを蘇らせた。デザイナーの勝利ってところだろう。それと、製品化を許可した担当役員に乾杯だ。よくやってくれました
厚くて重いドア&大径ホイールに見える設計部門の苦労
そうして誕生した現代版チャレンジャーの苦労したポイントをいくつかあげると、まずはでドアの厚み。現代における側面衝突の要件は厳しく、中にビームを入れたとしても厚みは避けられない。その分こうしたビッグクーペはドアが重くなってしまうわけだ。
それとホイールの大径化もそう。このクルマは20インチでロープロファイルのタイヤを履くが、当時のホイールサイズはデフォルトが15インチ、もしくは14インチだった。つまり、それを復元しようとすると、現代はタイヤがつくられていないのだ。なので、今の時代に合わせサイズを履くが、そうなると雰囲気が変わってしまう。そのためなるべくシンプルなホイールデザインにして、悪目立ちしないようにしているというわけだ。その辺を考察するだけでも、設計部門は大変だったと思う。
 開発の苦労が窺い知れるデザイン
開発の苦労が窺い知れるデザインレトロなアナログメーターと簡素な操作系スイッチがいい
2021年型のこのクルマはインテリアもイケている。特にドライバーオリエンテッドなコクピットはそうで、運転席に座るだけでワクワクする。有機的な曲線に包まれることで、宇宙船のコクピットにでもいるようだ。まぁ、宇宙船のコクピットに座ったことはないけど。
レトロなアナログメーターと簡素な操作系スイッチがいい。複雑な曲線の中にあってそのシンプルさが実にマッチしている。これが初期モノとの違い。そちらはフラットな造形の味気ない仕上がりで、外装につながるワクワクさは感じない。もちろん、その辺は趣味嗜好の違いだから「ボクは初期型の方が好き」という意見もあるだろう。よって両方座ってみて気に入った方を選ぶのが理想だ。
一般道からサーキットまで走れる現代版マッスルカー
今回取材したチャレンジャーは2021年型のR/Tとなる。かつて“ロード&トラック”、つまり、「一般道からサーキットまで走れるぜぃ」といった意味合いで使われていた言葉だ。
エンジンは5.7リッターV8 OHVを搭載。自然吸気のHEMIであることは言わずもがなだ。燃焼室の形が球形であることからこう名付けられた。最高出力は372hpを発揮する。アメリカ車ならではの大排気量エンジンが低回転から大トルクを発生させ、独特な世界観を味わせてくれる。アクセルを煽るたびに盛り上がるボンネットがたまらない。
そのエンジンをこのクルマは6速MTで動かすのも見逃せない。大排気量エンジンをいまどきMTで動かすのはレアだ。アメリカンブランドでも少なく、ヨーロッパメーカーではほぼ全滅となる。それじゃ扱い難いのかといえばそんなことはない。逆にトルクの太い分シフトチェンジは楽。どの回転域でもギアの入りは容易だ。それでいて、上までしっかり回せる場面ではクイックな手捌きでスポーティにシフトアップ&ダウンができる。この感覚が気持ちいいんだよね。まさにMTの醍醐味である。
クラッチはストロークが長すぎることなく、適度なポジションで切れる。リズミカルなクラッチ操作はけっこう感動的。ダッジブランドがアメリカでモータースポーツに参戦していた恩恵はこんなところにあるのかもしれない。

【プロフィール】
九島辰也 (クシマ タツヤ) / モータージャーナリスト兼コラムニスト
1964年生まれ。東京・自由が丘出身。外資系広告会社から転身、自動車雑誌業界へ。「Car EX(世界文化社 刊)」副編集長、「アメリカンSUV/ヨーロピアンSUV&WAGON(エイ出版社 刊)」編集長などを経験しフリーランスへ。その後メンズ誌「LEON(主婦と生活社 刊)」副編集長、フリーペーパー「go! gol.(ゴーゴル;パーゴルフ刊)」編集長、アリタリア航空機内誌日本語版「PASSIONE(パッショーネ)」編集長、メンズ誌MADURO(マデュロ)発行人・編集長などを経験する。2021年7月よりロングボード専門誌「NALU(ナルー)」編集長に就任。
また、傍らモータージャーナリスト活動を中心に、ファッション、旅、ゴルフ、葉巻、ボートといった分野のコラムなどを執筆。クリエイティブプロデューサーとしても様々な商品にも関わっている。
愛車はポルシェ911カレラ(2005年型)、三菱アウトランダーPHEV(2022年型)